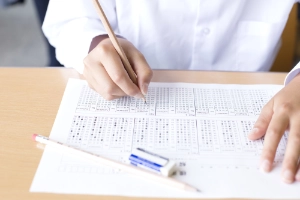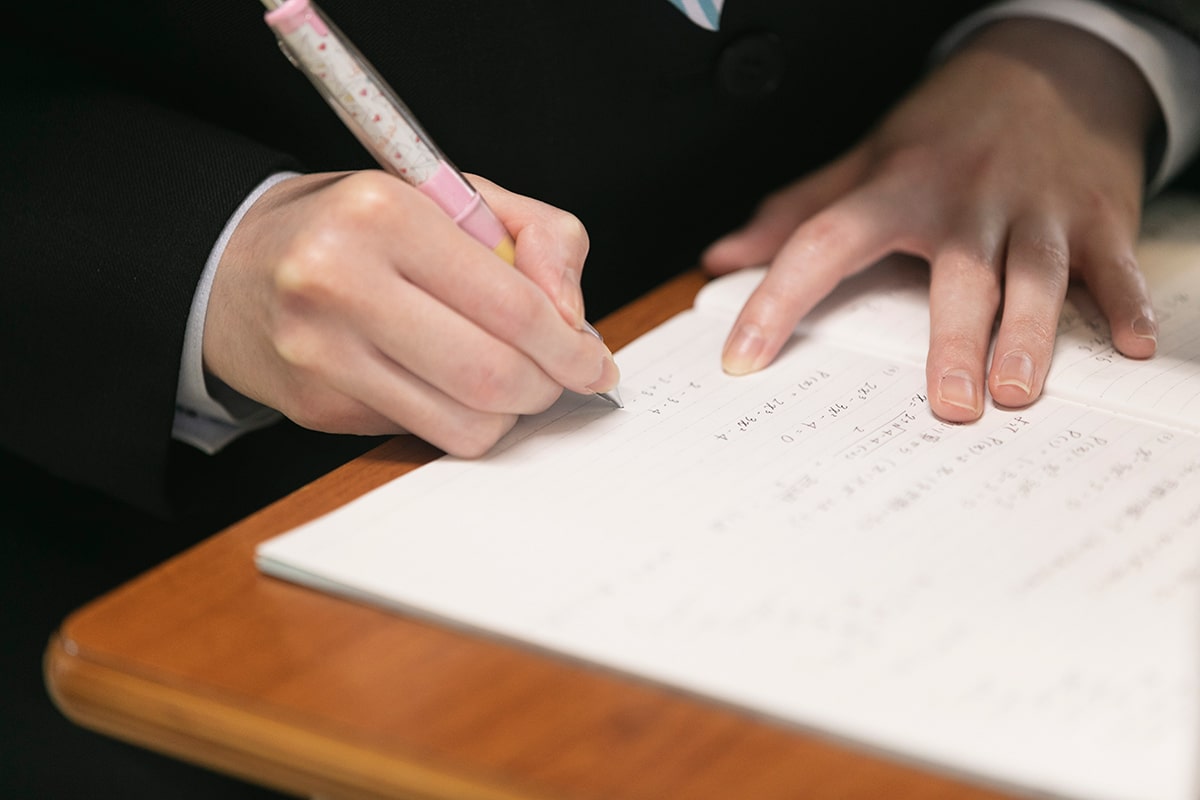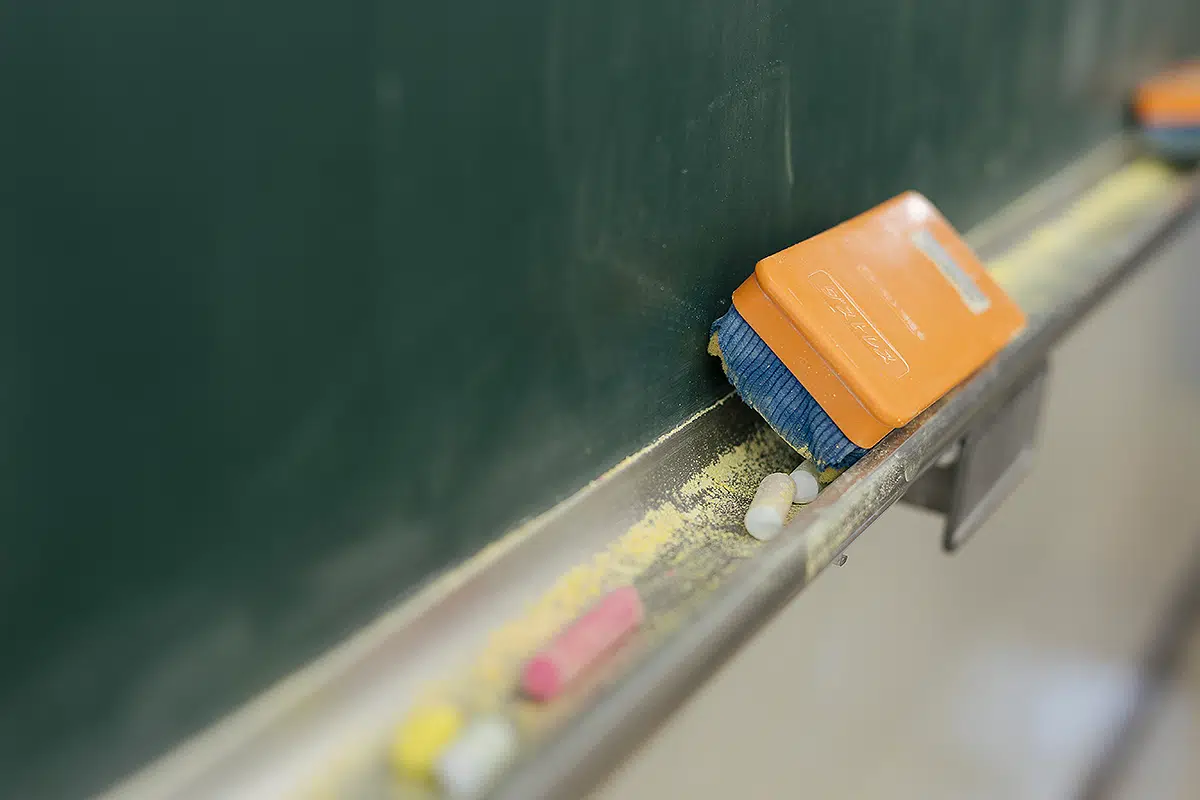心の中にある図形
三角形の構図という話題である。逆三角形は注意係数が高い。そのため、注意喚起の交通標識に使われている。美術品の中の三角形を考えてみよう。取り上げる作品は、「モナリザ」と「耳飾りの少女」である。
構図としての安定感のあるモナリザは、正面をむいた顔の額を頂点に、肩から肘をまげている腕を描いて実に安定した三角形の構図を創っている。鑑賞する人は安定した気持ちでこの絵を見てしまう。しかし、あの微笑をふくめて、気になるのは組んだ両手である。ここに、逆三角形の緊張感が仕組まれている。口元と組んだ手は大きな安定の中に、心のトリガ-として仕組まれている。謎のほほえみと言われるのは見る人の緊張がそう感じさせているからだ。
もう一つの作品、「耳飾りの少女」だが、この作品の視線が気になる人が多いことだろう。画面左側に偏る顔にある両目と口で逆三角形の構図を生み出している。鑑賞する人は間違いなくここに目を奪われる。常にこちらを見ているように感じる。そして、左側の目と真珠の耳飾りは、それぞれが明るい三角形と暗い三角形の頂点である。鑑賞者は見えない逆三角形を無理矢理意識させられて耳飾りに視線が吸い込まれていく。なで肩で自然な横向きの構図は安定しているので気にならない分、どうしても顔の表情が気になってしかたない。
美術作品を鑑賞する際に、無意識に誘導する力があるとすれば、逆三角形の緊張感が生み出す構図である。これは、三角形という図形が人間の認識の中で特別なフレ-ムであることを感じさせる。単純な図形の組み合わせで絵画、美術を見ているとすれば、言語理解にもこのようなフレ-ムが存在すると考えられる。多くの言語を操る人の脳には言語に関するフレ-ムが存在し、いろいろな言語を聞きながら、主語、述語、修飾語などを配置していくのだろう。このフレ-ムづくりこそ、語学習得のポイントなのかもしれない。
仏教世界を理解するための構図は曼荼羅である。近頃は思考方法の一つとしてマンダラシ-トなるものが存在している。仏様は民衆を救済するためにいろいろな姿に変身する。どんな風に変身して何を救ってくださるのかを理解する道具である。真ん中に大日如来を置いて、その変身する仏を周りにおいてどんな功徳があると、説明すると理解は早い。もともとの曼荼羅は砂絵のようなもので、理解してもらうと用が済みで、何も残らない。人間の頭にこんな理解のフレ-ムがあると考えていたのではないだろうか。ここまでくると、マンダラシ-トは実に理にかなっている。中心あるものは唯一無二と脳は自然と理解して、その達成に努力する。この認識フレ-ムに逆三角形を入れると、緊張感増し増しシ-トになりそうだ。へび年はシ-トにへびマ-クの三角形を書き込んで、達成度アップに取り組んでみてはどうだろうか。