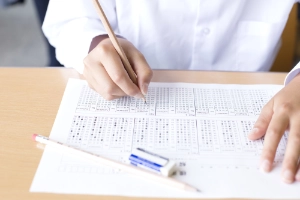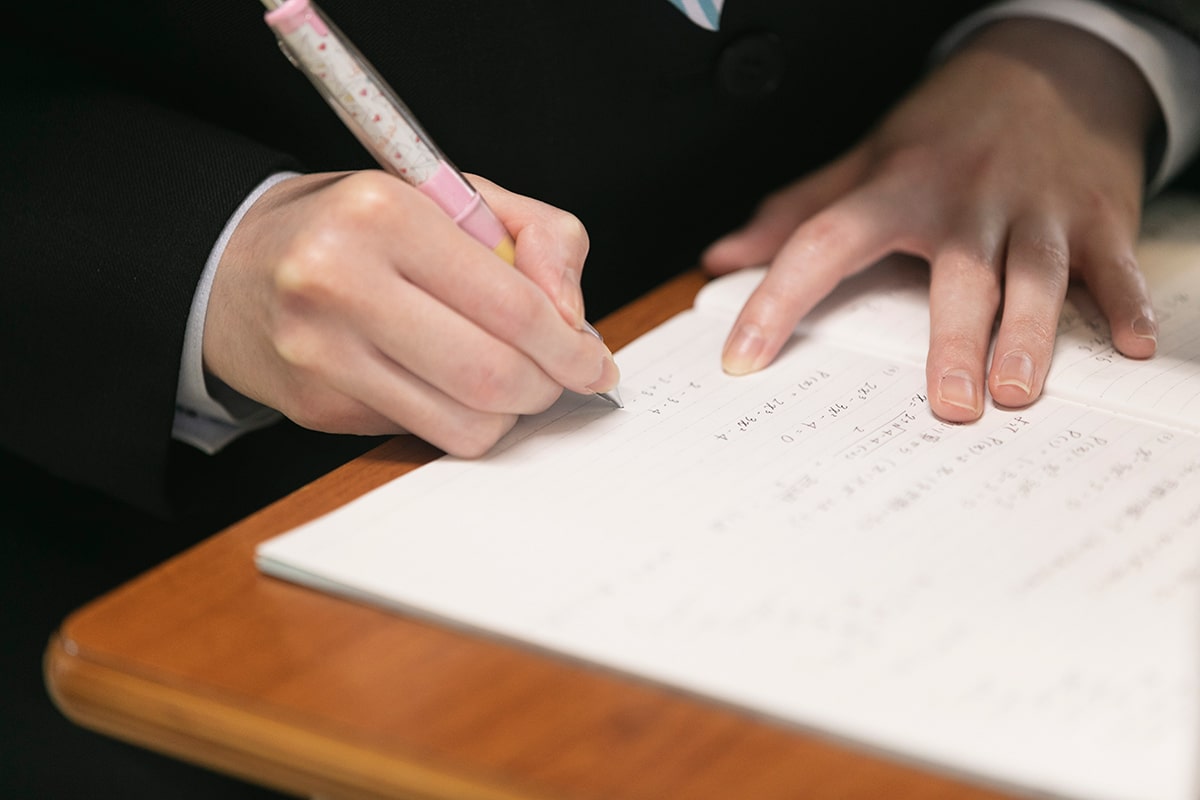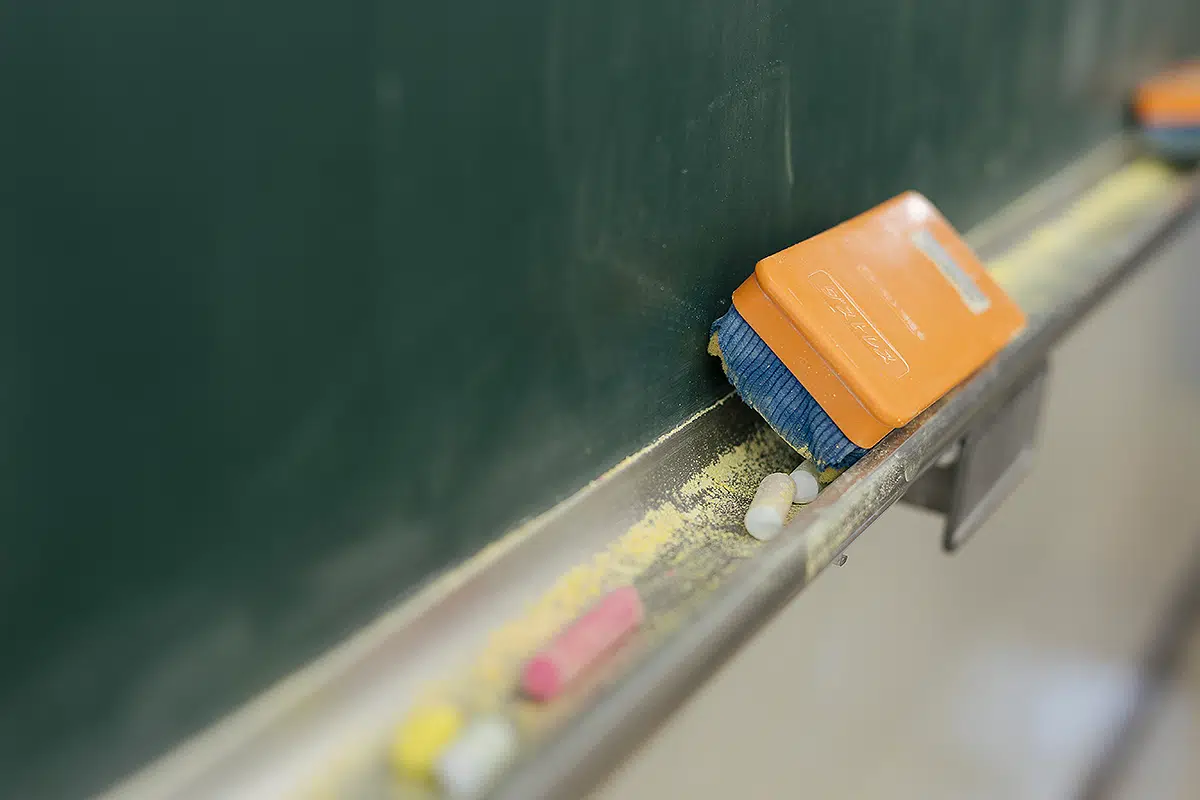離見の見
自分の姿を左右前後から、よくよく見なければならない。これが「離見の見(りけんのけん)」です。これは、「見所同見(けんじょどうけん)」とも言われます。詳しく見てみましょう。世阿弥の言葉で、「花鏡」に書かれています。
その部分を抜き出すと、「また舞に、目前心後といふことあり。目を前に見て、心を後ろに置け」となり。見所より見る所の風姿は、我が離見なり。しかればわが眼の見るところは、我見なり。離見の見にはあらず。離見の見にて見るところは、すなはち見所同心の見なり。その時は、我が姿を見得するなり。後ろ姿を覚えねば、姿の俗なるところをわきまえず。さるほどに離見の見にて見所同見となりて、不及目(ふぎょうもく)の身所まで見智して、五体相応の幽姿をなすべし。これすなわち、「心を後ろに置く」にてあらずや。」です。
ここで、言いたいことは、『観客の見る役者の演技は、離見(客観的に見られた自分の姿)である。「離見の見」、すなわち離見を自分自身で見ることが必要であり、自分の見る目が観客の見る目と一致することが重要である』なのです。
これは、客観的に自分を見る目、他人が自分を見る目をもつという意味です。教育用語の「メタ認知」と同じことのようです。舞を演じた後、その出来映えを評価した他人と自分の評価が同じに結果になる。自分の出した結果に必ず責任をもつという覚悟さえ感じます。これは世阿弥に限らず、日本人に根強い感覚だと思います。他人の目を意識するので、「世間が許さない」とか「お天道様に申し訳ない」の表現になります。結果の評価は他人がメインなのです。この言葉を根拠になぜか判断してしまいます。どこをどう見て(分析して)、どうするか(評価、改善)を明確にせず、とにかく他人の評価と自分のそれとが大きく違ってきたら、とりあえず、謝って責任をとるという流れなのです。
我々日本人は古来から自己と他己の評価の一致をめざした民族のようです。食い違うのは自己の見方のずれとか、項目の不足だと考えました。大多数の離見を想定して、自分を見ることを心がけたのです。自己のポイントや項目がずれるのと同じように「世間」も「お天道様」にもそれはあります。そう考えると、「離見」には客観性が保証されることが大切なのかもしれません。
鏡に映る姿も我見であって離見ではありません。姿をだれが見るかと具体的に想定し、その人の目になった時こそ、それは離見なのです。「同調圧力」は、我見して、まわりに忖度している状況です。社会生活に支障を与える行為はいただけないのは当たり前ですが、自分が我慢したり、譲歩しすぎるのも考えものです。「見る」バランスのとれた人なら、その場もうまく乗り越えられます。他人の目を気にしすぎるのもよくないが、まったく、無視するも困るのです。ちょうどよいところを取り上げるためにも、「離見の見」を身につけていきましょう。