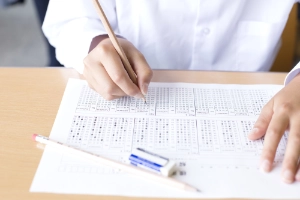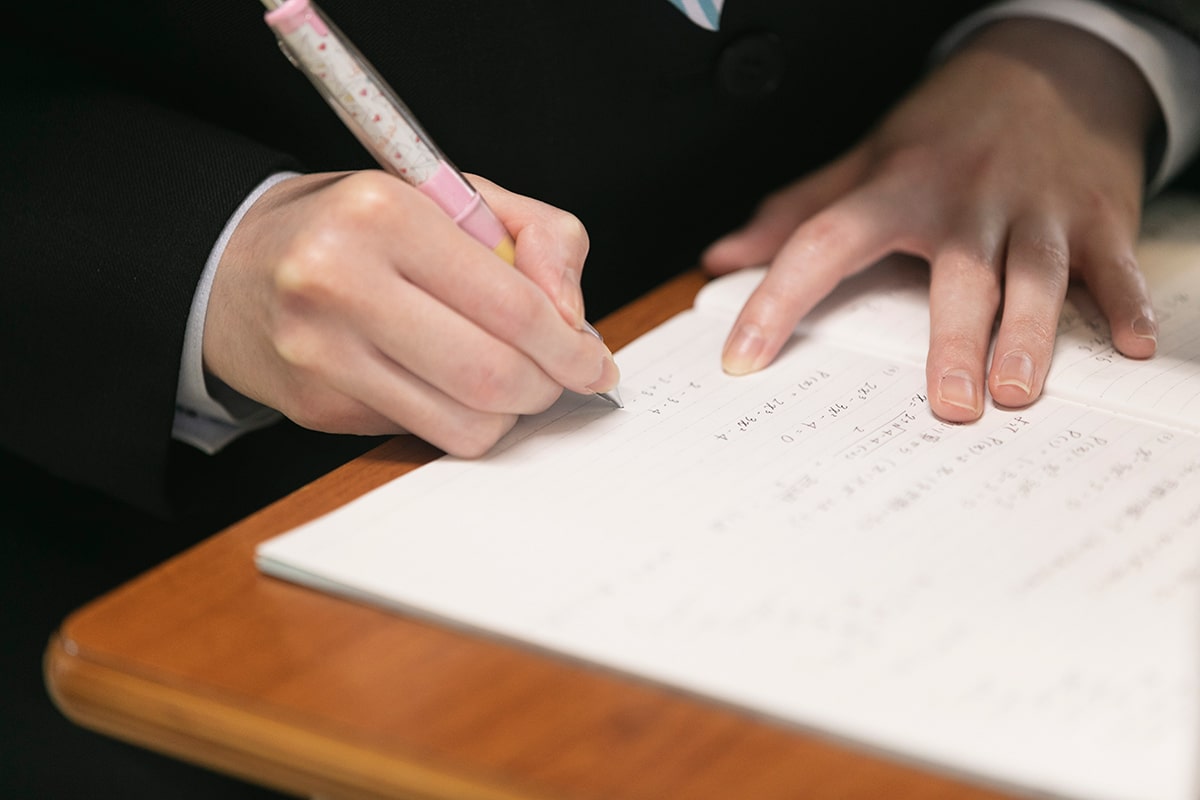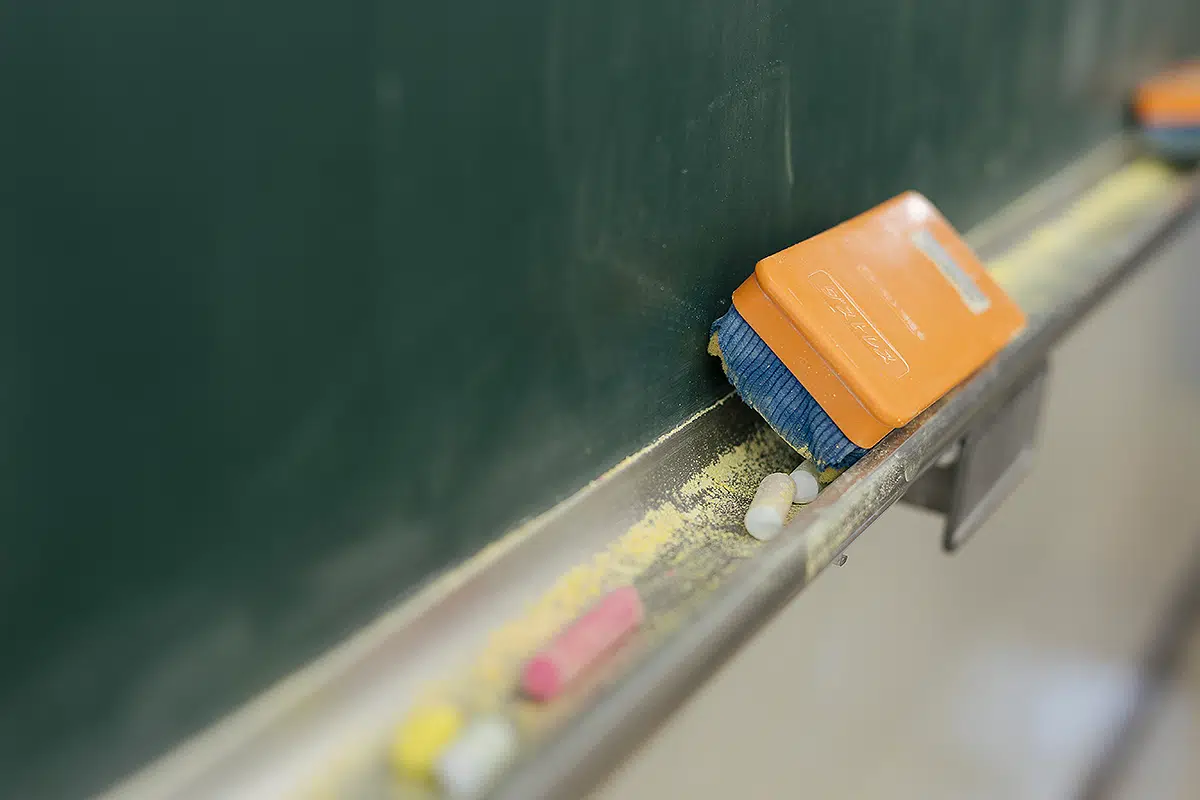生活記録と学級つくり
昭和の担任はとにかく忙しかった。漢字帳に日記帳、学級費や修学旅行代金集め、3月になれば会計報告をして学級費を返すのが当たり前だった。朝の学活に行くと、教卓には生活記録だけでなく、アンケ-トの紙、○検の申込用紙、それはそれはうずたかく積まれていた。2学期始めはなおさらで、読書感想文、生活文から始まり、○○俳句や○○の作文など、1週間は睡眠時間を削って読みまくるのが常だった。若さだけで乗り切っていたように思う。
さて、その中で生活記録は読む楽しみと、書く楽しみのあるものだった。生徒の「今」をそこから読み取り、どう返すかを考える。担任と生徒をつなぐ特別なものだった。当然、ここに書けるのは自分しかいないと生徒へのメッセ-ジに思いをこめた。今の学級の雰囲気を心配したり、来たるべき行事への取組を書いたりと生徒の毎日は忙しい。担任もそれに応えて毎日次から次へと書きまくった。生徒は仲間と作り上げる過程で自分の努力をだれかに認めてもらいたい。だから、生活記録に書く。それを認めて、励ましてあげるのは担任なのだ。自分の良さを気づかせるのによい機会だ。また、「いろいろあったけど、みんなとがんばれた」と書く生徒には、この一体感をつくる大切さを認め、強化したい。「人は一人では生きられません。仲間と手をとりあう瞬間、にぎった手を離さずに困難に立ち向かう時、そして、乗り越えたときの達成感を知りましたね。人生の宝というべき体験だと思います。」と書いた。
そういうつながりができたら、教師の思いは先回りして伝えるのもよい。学級をひっぱるメンバ-に後押しができる。先生が自分たちのことを考えてくれるという信頼の絆を深めることになる。学級づくりは生徒と教師の協働作業だが、私は運営委員会なるものをよく学級会の前に実施した。今度の学級の時間をどうするかを生徒に考えさせた。学活で学ぶものは、適応、進路、生活など学校生活をスム-ズに行う知識を身につけ、実践することである。この時間の取組が弱いと、学校生活の質が上がらない。発達段階に応じた生徒の自主性や達成感や成就感がうまれないことになる。特別活動は社会性の基盤づくりになるといっても過言ではない。自分たちでやろうとするクラスを育てたい。
つまり、自分たちで学級をつくり、運営するという気持ちが大切だ。そのためには、機会をとらえて、生徒とともにどんな学級にするかを話し合うことだ。行事準備の時間だけでなく、学校生活にどう適応するかを学び、それをお互い実践することも必要である。出し物を決めるにしても学級目標や全体目標との関連を考え、運営委員会で原案をつくり、話し合うというステップを踏んだ方がよいに決まっている。特別活動は自由度が高い。この時間の充実は、生徒の主体性が高まり、自己肯定感もあがる。ただし、どこをゴ-ルにするか、教師の関わり方も重要である。