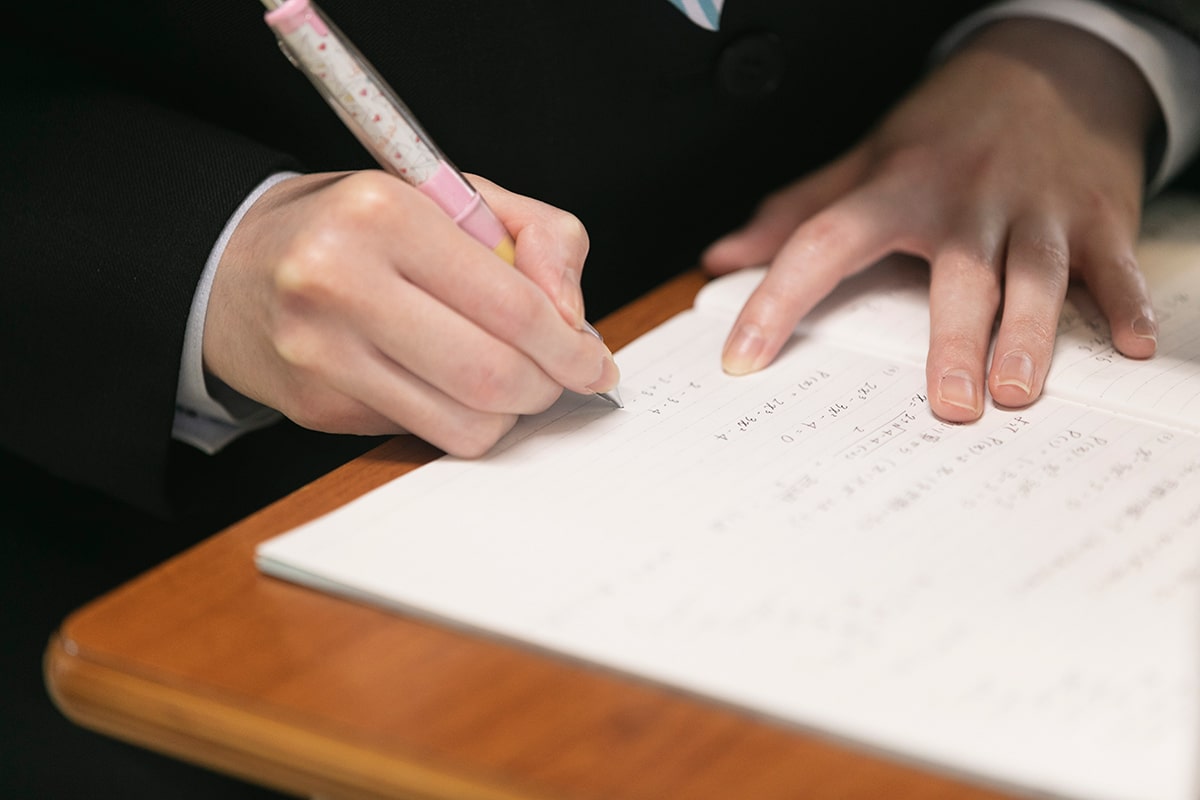光る君の舞台は宇治へ
源氏物語の作者紫式部を取り上げた今回の大河ドラマ「光る君へ」もいよいよ佳境に入った。道長の摂関政治がほぼ軌道に乗りつつある。源氏物語を書いて、中宮彰子サロンに花を添える藤式部の役目もほぼ終わった。
五十四帖のうち後半にあたる宇治を舞台とした物語を書き出すきっかけが先週の話で始まった。この十帖は別人の作とよく言われるが、今回の脚本はまぎれもなく紫式部が執筆したものとして、その書き出しのきっかけを描いた。
権勢を握りながらも、最愛の妻には先立たれ、過去の自分の過ちを、他人の子を抱くことで償う運命になる源氏。彼は果たして幸せだったのか?このきらびやかで美しい物語の結末にだれもが予想しない現実が重くのしかかる。物語的に「源氏はいつまでも幸せに暮らしました」としない式部のねらいは何だったのだろうか。考えてみれば、竹取物語も月へかぐや姫は帰り、地上での幸せは完結しない。夢や幻でなく、しっかりとした現実がそこにある。紫の上ははかなくも美しく亡くなる。最後まで彼女の出家を許さない源氏、愛するが故のわがまま、愛しているが故に思い切れない未練。最愛の人との別れのつらさを抱えて、源氏の最期はどうなるのか。だれもがここだけは見逃すまいと期待する。ご存じのとおり「雲隠」という題のみを置き、その死に一切ふれていない。
読者にしてみれば、この展開は期待外れも良いところである。ここまでの伏線回収はされても納得いかないことが多すぎる結末。光源氏の物語はキラキラからギラギラになり、最期はギリギリなのである。問題が山積みされたまま終わる物語も珍しい。源氏の子でありながら訳ありの子と源氏の孫であり宮様である子を登場させて、源氏物語は続く。真のおもしろさはここから始まる。あの有名なSFでさえも真っ青な話が始まる。自らの出生の疑いから仏道修行に志し、宇治を訪ね、大君たちと出会う薫、源氏の性格や行動を受け継ぎ、愛することに正直な匂宮、この二人の貴公子と宇治に住む美しい姫君との恋の話である。結末は悲恋である。しかも、愛するから拒否され、愛に迷うから拒否される。現実世界で正解を出すことはできないという結論である。父から中君の未来を託された大君は、自分を恋をも犠牲にして妹の幸せのために努力する。その結果は薫でなく匂宮と結ばれてしまう。死の間際に薫の気持ちは届くが、二人は結ばれることはない。残された中君は姉によく似た妹(浮舟)の存在を薫に打ち分け、薄幸の妹を幸せにしてほしいと語る。薫は浮舟に求愛するものの、彼女は匂宮を愛してしまう。二人の間で迷う浮舟は自殺未遂を起こし、尼になってしまう。ここでは出家を許されない紫の上とは違う生き方を描いている。
大河ではこの悲恋のモデルをだれにするのだろうか。「愛すれば、愛されれば、そこに必ず幸せがあるわけでない」のテ-マは、きらびやかさと対照的で実に重たい。